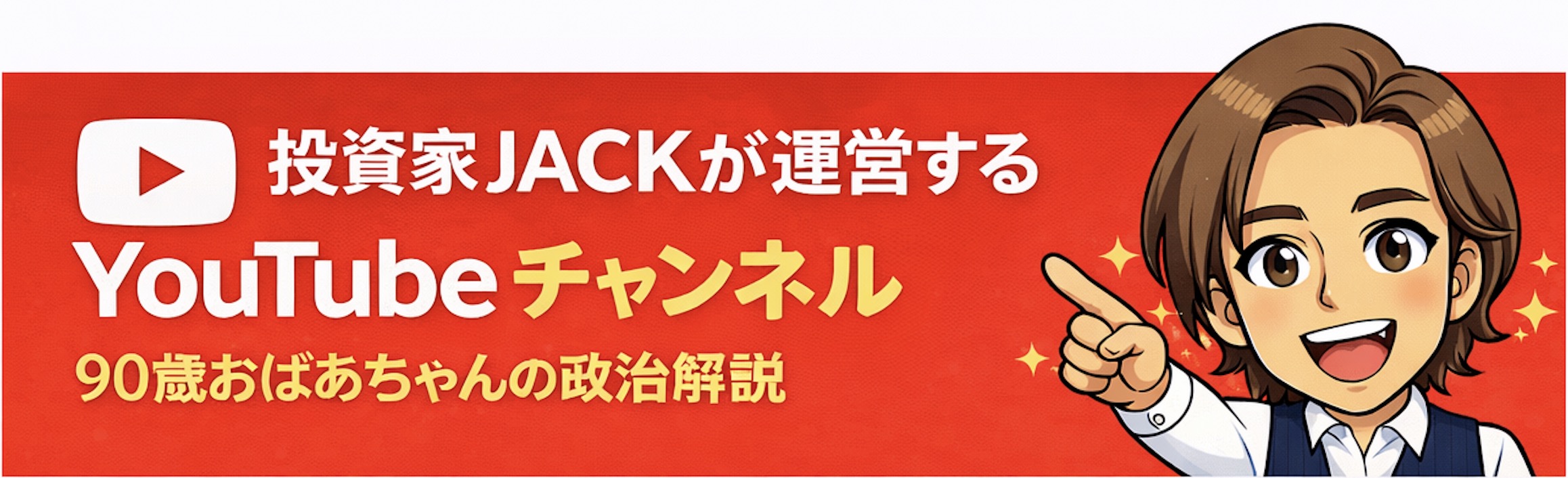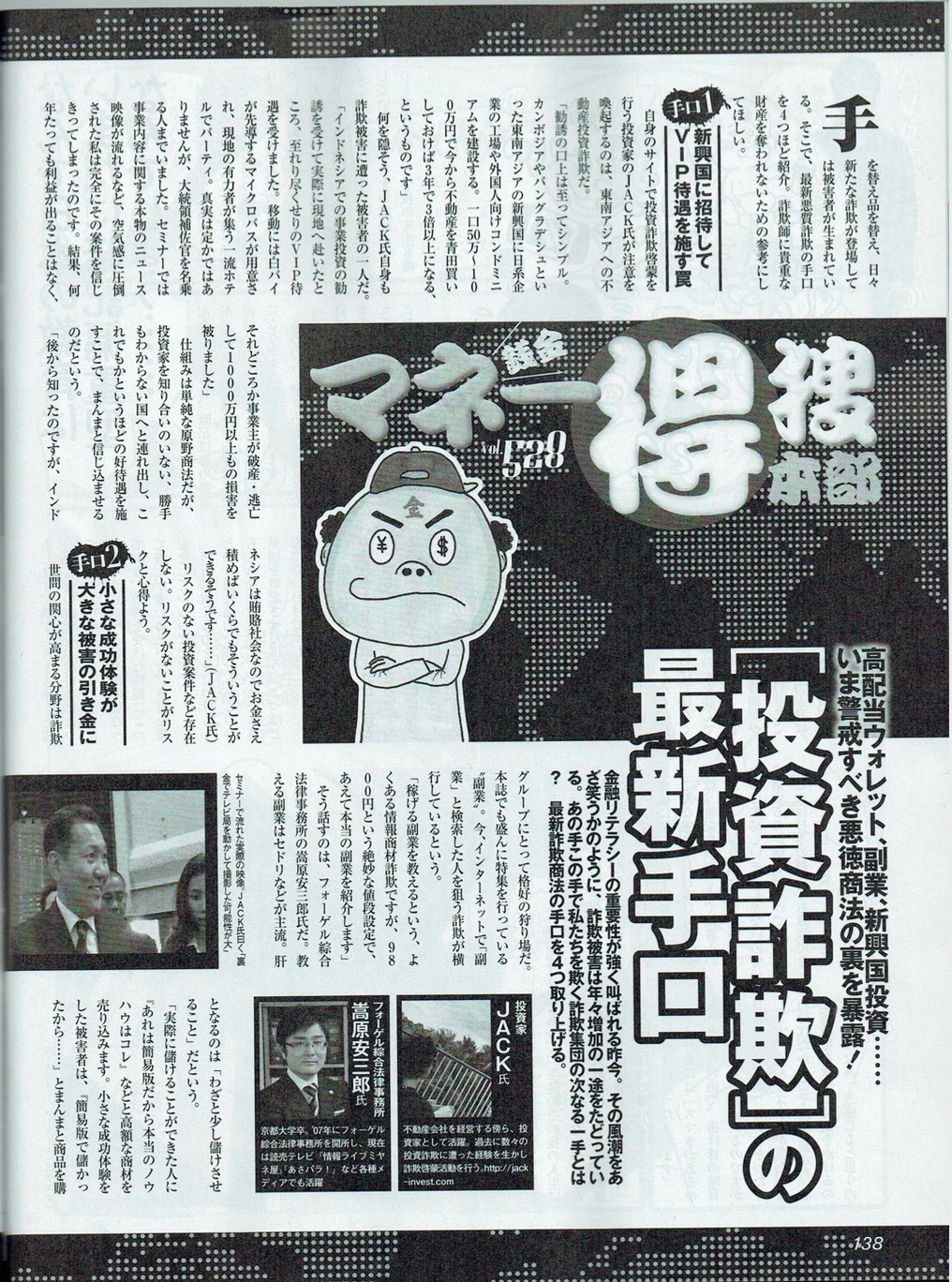「無料相談」の裏側に潜む高額手数料ビジネス
こんな経験はありませんか?
- FP(ファイナンシャルプランナー)に資産形成の相談をしたら、新築投資用ワンルームマンションの購入を強く勧められた
- 不動産投資セミナーに参加したら知り合ったFPからRL360°(ロイヤルロンドン)などのオフショア保険商品への加入を勧められた
- SNSで「不労所得」「資産形成」などをアピールする投稿から、高額商品の勧誘に繋がった
2025年現在でも、これらの手法は巧妙に進化しながら続いています。
FPと不動産販売会社の隠れた関係性
一部のファイナンシャルプランナー(FP)や金融アドバイザーと、
新築投資用ワンルームマンション販売会社(経営者や営業社員)は、
相互紹介システムを構築し、情報弱者から高額な手数料収入を得続けています。
特に2023年以降、金融庁による規制強化の動きがある中でも、
手法を変えながらこうした構造は存続しています。
オフショア長期積立商品と新築投資用ワンルームマンションに共通するのは
- 販売手数料が実質価値に対して不釣り合いに高額
- 長期契約によるロックイン効果
- 解約時の元本割れリスクが極めて高い
国内の資産運用商品における手数料開示の義務化が進む一方で、
これらの商品は開示が不十分なまま販売されるケースが多いのが現状です。
実例:負債の連鎖に陥るケース
実際の被害例では、以下のようなケースが報告されています。
- 新築ワンルームマンションを「家賃保証」と「節税」を理由にフルローンで複数契約
- 同時にRL360などの長期積立保険に加入し、毎月数万円の支払いが発生
- 「最初の2年だけ支払えば後は自由に減額できる」と説明されるが、実際には解約時に大幅な元本割れが発生
購入した物件の資産価値下落と金利上昇によるダブルパンチで、
多くの投資家が苦しい状況に直面しています。
誰が高額手数料を支払っているのか?
新築投資用ワンルームマンション1室の販売で数百万円、
RL360°などの長期積立商品で積立額の相当部分が手数料として支払われています。
なぜこれほど高額なのか?
答えは単純です:コスト(価格)とバリュー(価値)の不一致
これらの商品は多くの場合、支払う金額に見合った価値を提供していません。
そして、その差額は全て販売者側の利益となります。
身を守るための2つの鉄則
マネーリテラシー向上には時間がかかりますが、
とりあえずこの2つだけ覚えておけば大きな被害は避けられます。
鉄則①:
独立系FPからRL360やメティス等の海外長期積立商品を勧められても契約しない
金融庁は2023年以降、こうした商品の監視を強化しています。
国内の金融商品と比較して透明性が低く、
手数料構造が複雑なものには注意が必要です。
鉄則②:
フルローンでの新築投資用ワンルームマンションは購入しない
2025年の不動産市場では、築古物件でさえ事業収支が厳しい状況です。
家賃保証や税金対策だけを理由にした投資は避けるべきです。
投資の基本は「まずお金を減らさないこと」です。
情報が不足している状態で、
営業のプロフェッショナルと対峙するのは極めて危険です。
少なくとも以下の点を確認しましょう。
- 手数料の総額と構造を明確に開示してもらう
- 第三者(投資仲間や家族)の意見を必ず聞く
- 「急がなければならない」という心理的圧力には応じない
- 契約前に必ず冷却期間を設ける
資産形成は長期的な視点で、焦らず着実に進めることが重要です。